| 目次 |
| 前置き |
| あらすじ |
| この映画で感じたこと |
| 終わりの会で伝えよう! |
| 終わりに |
前置き
中学校教師のABCにんにんです。いつも訪問ありがとうございます
このブログでは教師の終わりの会を充実させるための話のネタを提供しています!今回は映画編です
2024年が始まりました!1月1日から大きな地震があり、世間は自粛ムードの中ではあるものの、いつも通りに生活することも大切だと考え、映画を観てブログを更新しています。
今回は『チャーリーとチョコレート工場』を観た感想から学級通信の内容を考えたいと思います。『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』を観るために再度観ました。そんな方も多いはずでは。それではいってみましょう!
あらすじ
世界中で大人気のウィリー・ウォンカ製のチョコレート。しかし、彼のチョコレート工場の中は完全非公開であり、謎に満ちていた。
ある日、ウォンカは「生産するチョコレートの中に5枚だけ金色のチケットを同封し、それを引き当てた子供は工場を見学する権利が与えられ、さらにそのうちの一人には想像を絶する素晴らしい『賞品』がつく」という告知を出した。世界中がチケット争奪で大騒ぎとなる中で運良く引き当てたのは、食いしん坊の肥満少年オーガスタス・グループ、お金持ちでわがままな少女ベルーカ・ソルト、いつもガムを噛んでいて勝利にこだわる少女バイオレット・ボーレガード、テレビ好きで反抗的な少年マイク・ティービー、そして家は貧しいが家族思いの心優しい少年チャーリー・バケットだった。
この映画で感じたこと
『チャーリーとチョコレート工場』では人の欲望についてキャラクターとともに描かれている作品だと感じました。
お菓子工場ではウィリー・ウォンカの極秘のレシピを、ほかのお菓子メーカーが送り込んだ産業スパイによって漏えいされ、他のメーカーによる自身が発明したお菓子の販売がエスカレート。
「生産するチョコレートの中に5枚だけ金色のチケットを同封し、それを引き当てた子供は工場を見学する権利が与えられ、さらにそのうちの一人には想像を絶する素晴らしい『賞品』がつく」という告知をウィリー・ウォンカが出すと、世界中がチケット争奪で大騒ぎに。
金色のチケットを運よく引き当てたのは、食いしん坊の肥満少年オーガスタス・グループ、お金持ちでわがままな少女ベルーカ・ソルト、いつもガムを噛んでいて勝利にこだわる少女バイオレット・ボーレガード、テレビ好きで反抗的な少年マイク・ティービーと、それぞれの欲望を前面に押し出すキャラクターの子どもたち。
主人公のチャーリー・バケットが引き当てた時の周囲の大人の反応。
上記のように欲望のまま行動する人物がたくさん登場し、特に特徴づけて描かれている金色のチケットを手に入れた4人の子どもたちに対し、主人公のチャーリー・バケットだけが、自分のチョコレートを家族に分け与えたり、金色のチケットをお金に換えようとするなど、欲望のまま行動している他の子どもたちとは違う、心の優しい人物として描かれていました。
「貧富の差」と「欲望」をリンクさせながら描き、欲望のまま動いた結果、ひどい仕打ちを受けてしまう子供たちの描き方は、イギリスの児童文学が原作ということもあって背徳的な喜びを見出す描き方に仕上がっているのかなとも思わされました。
因果応報。まさにそのような描かれ方がされているなと感じましたが、今の教育現場にはそれが薄いように感じます。やりたい放題の子どもがいてるのも事実です。そんな子どもを教育しきれない保護者の存在も…。現在に照らし合わせてこの映画を観てもリンクする部分があって興味深く感じました。
もしかすると日本の教育現場にもウィリー・ウォンカのような人物は必要なのかもしれませんね。
学級通信で伝えよう!
本日は『チャーリーとチョコレート工場』についてです。皆さん観たことはありますか?不思議な世界観のこの映画、笑いもありながら、皮肉な表現もあり、大人も子供も楽しめるような映画です。
登場する5人の子どもは、それぞれ特徴的な性格の子どもたちです。それぞれの性格に合わせた最後のシーンについて、「やりすぎだ」という声も聞こえそうなくらいの描写で描かれていました。そんな描写だったので、小さかった頃の私はこの映画を初めて観た時「怖かった」という思い出があります。小さい子にとってはトラウマレベルの描写かもしれませんね。
最近の学校現場はしからない教育に変化していきました。私の学生時代は、悪いことをした生徒に対して先生方が怒鳴っていることがよくありましたが、最近は怒鳴ることなく「諭す」ことの方が多くなっています。怒鳴る先生やしかる先生を本当に見なくなりました。
とてもいいことだと思いますが、一方で自分勝手な生徒の行動も多くなっているように感じているのは私だけでしょうか。しかられて気づかされたことがたくさんあった私にとって、しかるという取り組みも大切なのではと考えさせられます。
人は必ず失敗します。失敗を経験して成長していくのが人です。成功ももちろん大切なことですが、私の経験上失敗から学ぶことの方が多いように感じています。今の学生はその失敗という認識を自ら理解していかなければいけない環境になっているのかなと感じています。皆さんはどう感じていますか?
『チャーリーとチョコレート工場』で登場する5人の子どもは、それぞれ自分勝手に行動します。その報いを受けるかのようにウンパ・ルンパの歌と踊りとともにひどい仕打ちを受けるんです。一見かわいそうに感じますが、そうでもしないと彼ら(保護者も含め)は現状の無礼な行為を理解できなかったかもしれません。
そう考えると、学校現場でしかられることはいいことなのかもしれないし、こんな世の中になってもなおしかってくれる先生の存在は、とてもありがたい存在なのかもしれないなと思いながらこの映画を観ていました。
もちろんしかられるような取り組みはするべきではありません。褒められる取り組みができれば文句なしです。でもみなさんはまだまだ成長過程にあります。失敗した時、しかられた時に素直に聞き入れて、次の行動に反映させることができるステキな人になってください!ウンパ・ルンパもそれを望んでいると思います。
ちなみに主人公のチャーリーは自分のチョコレートを家族に分け与えたり、金色のチケットをお金に換えようとするなど、欲望のまま行動している他の子どもたちとは違う、心の優しい人物として描かれていました。
チャーリーのこのような取り組みは、これからの皆さんの人生の教訓になるかもしれませんね。いい作品なので、ぜひ観てみてください。
終わりに
以上、『チャーリーとチョコレート工場』についての学級通信の内容でした!
今回は「しかる」を裏設定にしてお話を考えてみました。最近は本当にしかられなくなったと感じています。保護者にもしかられなければ、雷親父のような近所の方もおられない。学校の先生すらしかることをやめてしまっていては、悪いことをすれば警察に直結してしまいます。そんな世の中になりつつあるのを危惧している私の目線からの内容でした。
まだ見ていない方はぜひ観てみてください!
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。

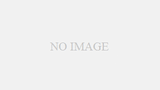
コメント